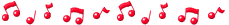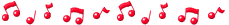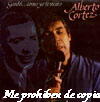
|
|
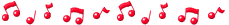
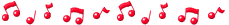
 僕は市場のおしゃべり男吟遊詩人<ALBERTO CORTEZ> 僕は市場のおしゃべり男吟遊詩人<ALBERTO CORTEZ> |
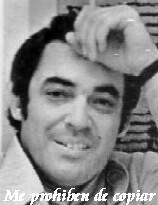 しっかしたなかにも庶民的な味わいのある歌声で人気のある歌手がいます。私がスペインで買ったレコード「VIVA 87」の中でも「HASTA CUANDO」の題名で歌うのがシンガーソングライターのアルベート・コルテスです。 しっかしたなかにも庶民的な味わいのある歌声で人気のある歌手がいます。私がスペインで買ったレコード「VIVA 87」の中でも「HASTA CUANDO」の題名で歌うのがシンガーソングライターのアルベート・コルテスです。彼は1940年3月11日にアルゼンチンのパンパ地方のランクル村で生まれました。父はスペイン系、母はイタリア人で、ブエノスアイレスで法律を学んでいましたが、音楽の道を志、大学を中退しました。 1960年にヨーロッパに渡り、日本でも竹越みち子(力道山の経営していたナイトクラブ「リキ」の専属歌手)が「スク・スク・スキ」で和製スクスクとして知られていますが、「スクスク」で世界を席捲して有名になりました。もとはボリビア民謡です。 歌にはメッセージが必要と考え、父の故郷のスペインに行き、アントニオ・マチャードやローベ・デ・ベガなどのスペインを代表する詩人の詩に作曲をしました。吟遊詩人の如く、語りかける歌い方が特徴となりました。その代表的なアルバムが1976年発表の「SOY UN CHARLATAN DE FERIA(僕は市場のおしゃべり男)」です。このアルバムは全てアルベート・コルテスが作曲した作品です。特に私は「PAJARITA DE PAPEL」が印象的です。 |
 売れっ子男性シンガーソングライター<JOSE LUIS PERALES> 売れっ子男性シンガーソングライター<JOSE LUIS PERALES> |
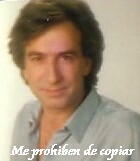 1992年にアンダルシアのセビジャで万国博覧会が開催されました。往復夜行バスという強行軍で閉会間際の1992年10月初めに行きました。その会場の一角にデイスコテカのコーナーがあり、老若男女が楽しそうに踊っていました。その時に流れていた曲はホセ・ルイス・ペラ−レスの「アメリカ」という曲でした。 1992年にアンダルシアのセビジャで万国博覧会が開催されました。往復夜行バスという強行軍で閉会間際の1992年10月初めに行きました。その会場の一角にデイスコテカのコーナーがあり、老若男女が楽しそうに踊っていました。その時に流れていた曲はホセ・ルイス・ペラ−レスの「アメリカ」という曲でした。彼は、1945年1月18日にスペインのクエンカのカステホンで生まれました。工業大学で放送技術と電気工学を学びながらトゥーナ(街中を演奏しながら歌う若者のグループ)に参加しました。卒業後にマドリードに行き、作曲を続けていました。1974年にジャネットが歌った映画「カラスの飼育」(カルロスサウラ監督)の主題歌「ポル・ケ・テバ」がスペインを始めヨーロッパや中南米で大ヒットとなり、一躍有名になりました。 彼自身がシンガーソングライターとしてレコードデビューしたのは1974年です。1982年に発表された「Entrel el agua y el fuego(情熱と涙のあいだで)」は好きなアルバムです。特に「DIME(Preguntandole a Dios・ 神様に尋ねるように私に言って)」はやさしい歌声と歌唱力を充分楽しむことができます。また、アルバム「AMERICA」は1991年に日本でも発売されました。 |
 国民的詩人アントニオ・マチャードの詩で歌う 国民的詩人アントニオ・マチャードの詩で歌う<Joan Manuel Serrat> |
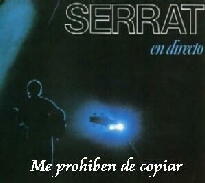 アントニオマチャードを知らないスペイン人はいないのではと思うほどの国民的な詩人です。1875年にスペイン南部のセビリアで生まれました。スペインでは「98年世代(米西戦争の敗北に象徴されるスペインの後進性の痛感し、近代化を模索した知識人たち)」に属します。簡潔な詩形と素朴な詩語を特徴としています。 アントニオマチャードを知らないスペイン人はいないのではと思うほどの国民的な詩人です。1875年にスペイン南部のセビリアで生まれました。スペインでは「98年世代(米西戦争の敗北に象徴されるスペインの後進性の痛感し、近代化を模索した知識人たち)」に属します。簡潔な詩形と素朴な詩語を特徴としています。彼の作品中で最も有名な詩集が「COMPOS DE CASTELLA(カステイジャーの大地)」です。荒涼としたソリアなどのカステイジャの風景を中心に描いた詩集です。私もマドリードのグランビアにある本屋「CASA DE LIBRO」で買い求めました。 その詩集の「PROVERBIOS Y CANTARES XXIX」に曲をつけて有名になった歌手がいます。その歌手の名前は「JOAN MANUEL SERRAT(フォアン・マニュエル・セラート)」で、曲の題名は「CANTARES」です。 日本では高村光太郎の「道程」の詩と同じ趣があります。ソリアには「アントニオマチャード」と名付けられた高級国営宿舎・パラドールもあり、その他にもEnrique mantoyaを始めとしてアントニオマチャードの詩に曲を付けた歌手は多く、それだけスペインの国民的な詩人だと言うこができると思います。 |