
|
〜映画が好きな君は素敵だ〜 |
|
|
☆『ほろよい人生』【1933年(昭和8年)木村荘十二監督】 駅のホームでアイスクリームを売子のトク吉(藤原釜足)は、同じホームでビール売子のエミコ(千葉早智子)とビアホールを持つことを夢見ていますが、エミコ音楽大学の学生の アサオ(大川平八郎)と恋愛関係にあります。アサオは流行歌を作曲したことで、大学を退校させられますが、印税でエミコと結婚します。失意のトク吉ですが、盗難品を取戻したお礼で、念願のビアーホルを開業します。その店の名前は「エミコ」で、彼女の幸せを陰ながら応援し、ビールで喉の渇きを干します。 駅のホームでアイスクリームを売子のトク吉(藤原釜足)は、同じホームでビール売子のエミコ(千葉早智子)とビアホールを持つことを夢見ていますが、エミコ音楽大学の学生の アサオ(大川平八郎)と恋愛関係にあります。アサオは流行歌を作曲したことで、大学を退校させられますが、印税でエミコと結婚します。失意のトク吉ですが、盗難品を取戻したお礼で、念願のビアーホルを開業します。その店の名前は「エミコ」で、彼女の幸せを陰ながら応援し、ビールで喉の渇きを干します。日本映画初期のミュージカル・コメディ映画で、現在の東宝の前身であるP.C.Lの第1回製作映画です。P.C.L.の経営者が「大日本麦酒」の取締役で、ビールの宣伝も兼ねたタイアップ作品でもあります。なお、この作品は東京音楽大学在籍中の藤山一郎さんの「酒は涙かため息か」を吹き込んだ事件がヒントになったとされています。私は1982年に開催された京橋のフィルセンターの「日本映画史研究2 東宝映画50年の歩み1」の上映でこの映画を初めて観て以来、34年ぶりでしたが、そのスピーディさとモダンさには驚愕します。 |
☆『女優と詩人』【1935年(昭和10年)成瀬巳喜男監督】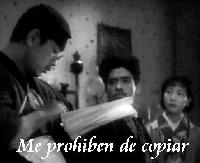 中野実さんの原作の映画化で成瀬巳喜男監督が『乙女ごゝろ三人姉妹』(1935年)に続くトーキー第二作目です。主演の舞台女優千絵子は、成瀬巳喜男監督と後に結婚する千葉早智子さんが出演しています。 中野実さんの原作の映画化で成瀬巳喜男監督が『乙女ごゝろ三人姉妹』(1935年)に続くトーキー第二作目です。主演の舞台女優千絵子は、成瀬巳喜男監督と後に結婚する千葉早智子さんが出演しています。物語は売れない童謡作家の二ツ木月風(宇留木浩)と舞台女優千絵子(千葉早智子)との夫婦を通して描く風刺喜劇です。生活力のある千絵子に代わり月風が家事の仕事をし、千絵子に頭が上らず夫婦喧嘩もしたことがありません。しかし、月風の友人の三文文士の能勢梅童(藤原釜足)が下宿することになり、本格的な夫婦喧嘩となります。だが、喧嘩を通して仲睦まくなります。 噂好きの主婦・お浜さん役の若き日の戸田春子さんや能勢梅童役の藤原鎌足さんが好演しています。先月(2003年11月)他界された佐伯秀男がダンディで自殺未遂を図る青年役で出演しており感慨深いものがありました。 |
☆『噂の娘』【1935年(昭和10年)成瀬巳喜男監督】 ロシアの作家・チェーホフ原作の「桜の園」をベースにした成瀬巳喜男監督のオリジナル脚本による作品です。没落していく灘屋という老舗の酒屋を舞台に、実家の商売を手伝うしっかり者の姉・邦江(千葉早智子)と自由奔放に遊び周る妹の紀美子(梅園龍子)との対照的な性格の姉妹を描いた映画です。 ロシアの作家・チェーホフ原作の「桜の園」をベースにした成瀬巳喜男監督のオリジナル脚本による作品です。没落していく灘屋という老舗の酒屋を舞台に、実家の商売を手伝うしっかり者の姉・邦江(千葉早智子)と自由奔放に遊び周る妹の紀美子(梅園龍子)との対照的な性格の姉妹を描いた映画です。没落していく老舗の酒屋、性格の正反対の姉妹、妻と別れた父親(御橋公)とその恋人(伊藤智子)、商売を婿任せの先代(汐見洋)などの人生の喜怒哀楽を五十数分間に見事に描き出された作品です。いつも深刻な面持ちの御橋公さんが様々な苦悩に立向かう婿役を好演しています。 |
☆『朝の並木道』【1936年(昭和11年)成瀬巳喜男監督】 千代(千葉早智子)は、親友の久子(赤木蘭子)を頼って上京しましたが、久子がカフェーの女給をしているので驚かされます。しかし、厳しい現実のなかで千代は職探しをします。苦労の甲斐も無く、失業者のあふれる東京では千代も女給になるしか道はありませんでした。千代は親切な常連客の小川(大川平八郎)に心惹かれますが、小川の仙台への転勤で千代は一人取り残されます。しかし、教えてもらった仙台の住所の紙を川に流し、眩しい朝の青空のなか新しい仕事をも求めて、歩み始める千代でした。 千代(千葉早智子)は、親友の久子(赤木蘭子)を頼って上京しましたが、久子がカフェーの女給をしているので驚かされます。しかし、厳しい現実のなかで千代は職探しをします。苦労の甲斐も無く、失業者のあふれる東京では千代も女給になるしか道はありませんでした。千代は親切な常連客の小川(大川平八郎)に心惹かれますが、小川の仙台への転勤で千代は一人取り残されます。しかし、教えてもらった仙台の住所の紙を川に流し、眩しい朝の青空のなか新しい仕事をも求めて、歩み始める千代でした。千代の田舎の風景、譲許して高揚するして歩く上野や銀座、仕事探しに歩く丸の内のオフィス街や清澄橋あたりの風景が丁寧に描かれています。また、厳しい現実の中でも千代の明るい気持ちのラストシーンは印象的で、成瀬巳喜男監督作品でも私の好きな映画です。 |
☆『母なればこそ』【1936年(昭和11年)木村荘十二監督】 中道家は、母のちか子(伊藤智子)は金策に駆け巡るほど苦しい中、父の死(御橋公)により没落しる。長女正子(千葉早智子)は一家を支えるために芸妓として働ることになる。そんな折、松井(北沢彪)は小栄龍と再会し、子供ができるが、松井の父(滝沢修)は結婚を許さない。正子は一人で苦労して子供を育てるが、いつも彼女を見守る運転手の山岸(丸山定夫)の姿があった。 中道家は、母のちか子(伊藤智子)は金策に駆け巡るほど苦しい中、父の死(御橋公)により没落しる。長女正子(千葉早智子)は一家を支えるために芸妓として働ることになる。そんな折、松井(北沢彪)は小栄龍と再会し、子供ができるが、松井の父(滝沢修)は結婚を許さない。正子は一人で苦労して子供を育てるが、いつも彼女を見守る運転手の山岸(丸山定夫)の姿があった。原作は川口松太郎で、母もの映画です。誰も悪人がいないい映画で、社会規範や時代に翻弄されて、皆が幸福になれないが、一人ひとりの座標軸が重要だと感じます。 |
☆『青春部隊』【1937年(昭和12年)松井稔監督】 喫茶店「ジヨリ・モンド」を舞台した大学生を中心とした恋愛と友情をミュージカル仕立てに描いた作品です。 喫茶店「ジヨリ・モンド」を舞台した大学生を中心とした恋愛と友情をミュージカル仕立てに描いた作品です。映画には千葉早智子さん、佐伯秀男さん、大川平八郎さん、堤真佐子さん、江戸川蘭子さんを初めてとした青春スターが多数出演し、歌声を披露しています。また、昭和10年代の東京の風景を楽しめます。東宝の映画の原点がPCL時代の青春映画にあることが、この映画を観て改めて感じました。 |
☆『鉄の兄弟』【1939年(昭和14年)渡辺邦男監督】 藤井大吉(高田稔)は、夜学に通う弟の民夫(伊東薫)とアパートでの二人暮らしです。そこに垢抜けた女性・かほる(千葉早智子)が同じアパートに引っ越してきます。かおるは子供を引き取るために元夫の小坂(三木利夫)にお金を要求され、途方に暮れますが、それを聞いていた民夫が、兄に内緒でお金を貸します。それを知った大吉は、激怒してかおるに部屋に講義に行きますが、事情を知り、お金を与えたことを納得します。その日に電報で民夫の招集通知が来ます。壮行会の席に脅しに来た小坂は、大吉の説得で改心し、総会の席に加わります。 藤井大吉(高田稔)は、夜学に通う弟の民夫(伊東薫)とアパートでの二人暮らしです。そこに垢抜けた女性・かほる(千葉早智子)が同じアパートに引っ越してきます。かおるは子供を引き取るために元夫の小坂(三木利夫)にお金を要求され、途方に暮れますが、それを聞いていた民夫が、兄に内緒でお金を貸します。それを知った大吉は、激怒してかおるに部屋に講義に行きますが、事情を知り、お金を与えたことを納得します。その日に電報で民夫の招集通知が来ます。壮行会の席に脅しに来た小坂は、大吉の説得で改心し、総会の席に加わります。中野実原作小説の映画化です。太平洋戦争を目の前にした戦争を第一義的に考える時代の人間の倫理観を描いた作品です。かほる役の千葉早智さんは、「ほろよひ人生』(1933年)などの映画に出演した戦前に活躍した女優さんで、成瀬巳喜男監督の元夫人でもあります。戦後は高級料理店を渋谷で開業するなど実業家として活躍しました。私は30年目に三百人劇場での成瀬巳喜男監督特集でロングインタビューの冊子での若々しく綺麗な千葉早智子さんを思い出します。 |
☆『女の教室』【1939年(昭和14年)阿部豊監督】 七人の医学部の女子学生たちの卒業までの葛藤、卒業後のそれぞれの新たな人生の苦闘、戦争に翻弄される姿を”グランドホテル方式”で描きます。 七人の医学部の女子学生たちの卒業までの葛藤、卒業後のそれぞれの新たな人生の苦闘、戦争に翻弄される姿を”グランドホテル方式”で描きます。「学校の巻」「人生の巻」「戦争の巻」の3部構成です。「学校の巻」の卒業式の校長(藤間房子さん)祝辞「学校での”女の教室”は終わるが、人生での”女の教室”が新たに始まる」が主題にしています。七人の人生を演じる女優陣が個性を生かし好演し、80年前の映画とは思えない脚本と演出です。女性の置かれた時代背景を的確に捉えた内容。原作は『母の曲』などの著者の吉屋信子さんで、1922年の『海の極みまで』〜1968年の『花の恋人たち』の戦前38本と戦後15本の合計53本が映画化されています。 |
☆『母の地図』【1942年(昭和17年)島津保次郎監督】 戦争によって没落した岸一家は長野県から東京に移り住み、困窮を極めていた生活の苦闘と母親(杉村春子)の子供への愛情を描いた作品です。長男(三井田健)は満州で事業に失敗し、次男(大日方伝)は招集され、次女(花井蘭子)は病床に臥します。また、三女桐江(原節子)も好きな男性北野(森雅之)と専務の息子との縁談に挟まれます。若き日の森雅之が原節子の恋人役で映画デビューした作品でもあります。島津保次郎監督作品は、戦中でありながら人間の機微を見事に描いた監督として忘れることができません。 戦争によって没落した岸一家は長野県から東京に移り住み、困窮を極めていた生活の苦闘と母親(杉村春子)の子供への愛情を描いた作品です。長男(三井田健)は満州で事業に失敗し、次男(大日方伝)は招集され、次女(花井蘭子)は病床に臥します。また、三女桐江(原節子)も好きな男性北野(森雅之)と専務の息子との縁談に挟まれます。若き日の森雅之が原節子の恋人役で映画デビューした作品でもあります。島津保次郎監督作品は、戦中でありながら人間の機微を見事に描いた監督として忘れることができません。銀座の繁華街、丸の内や有楽町のビジネス街、混雑する上野駅や東京駅、蒲田付近の住宅街など昭和17年頃の東京の風景が楽しめます。さらに東京市電13系統の”ラッシュの模様”、東急電鉄の「モハ510形」、初の愛称名を持つ列車、東京発下関行きの特別急行「櫻」など興味津々でした。 また、東宝退社(引退)直前の千葉早智子さんが槇江役で出演しています。東宝退社直前の出演で、1986年の三百人劇場の特集「成瀬巳喜男監督」でロングインタビュー記事を掲載では、引退理由を原節子さんらの新人の台頭よりも、七年の別居生活後の成瀬巳喜男監督の再婚と戦時中の慰問で留守を嫌がる母のためと語っています。 |

|